

この記事からわかる3つのこと
・『ドン・キホーテ』の歴史と、プティパやゴルスキーなど振付家による改訂の流れ
・作品のあらすじと登場人物、そして見どころとなる代表的なシーン
・各国の有名バレエ団による上演や映像作品、DVDで楽しむ方法
スペインは、太陽や海、闘牛士、陽気な人々といった華やかなイメージの国。寒いロシアの人々にとっては憧れの存在であり、1869年にモスクワで初演された『ドン・キホーテ』は大成功を収めました。
当時のモスクワは首都サンクト・ペテルブルクに比べ庶民的な街で、舞台に描かれた明るい人々の姿は観客の共感を呼びました。1871年にはプティパ自身がペテルブルクで改訂版を上演し、これが現在まで続く上演の原型となっています。
バレエを初めて観る人にオススメなのが、この『ドン・キホーテ』です。底抜けに明るく、華やかで、テクニックに優れたダンサーが次々と登場します。ストーリーを知らなくても十分に楽しめますが、あらすじを知っておくと10倍楽しめる作品です。
今回は、世界中で愛される『ドン・キホーテ』の魅力を、成り立ちから名場面まで順を追ってご紹介します。少し情報量は多めですが、読みやすく章立てしています。
元劇団四季、テーマパークダンサー。舞台、特にバレエを観に行くのが大好きで、年間100公演観に行った記録あり
※ 3分ほどで読み終わります。
『ドン・キホーテ』が多くの人に愛される理由
バレエ『ドン・キホーテ』は、明るくコミカルな雰囲気と分かりやすいストーリーで知られています。スペインの庶民的な祭りを舞台に、情熱的な踊りや居酒屋での愉快な場面が展開し、物語もシンプルで楽しいため、初めてバレエを見る方にもオススメの演目です。壮大な白鳥や妖精が登場する幻想的な作品(『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』など)とは異なり、『ドン・キホーテ』は現実味のある喜劇で、お芝居の要素もふんだんに盛り込まれています。主人公カップルの恋のドタバタ劇を中心に、年配の騎士ドン・キホーテや個性豊かな脇役たちが物語を盛り上げ、観客を笑顔にしてくれます。
また、クラシック・バレエの高度なテクニックと情熱的なスペイン舞踊、コミカルなお芝居が同時に楽しめる華やかな演目としても人気です。バレエファンにとっては、劇中で披露される超絶技巧の数々(特に結婚式の場面でのグラン・パ・ド・ドゥ)は見どころ満載であり、一方でストーリーは難解ではないため初心者でも退屈しません。こうした分かりやすさと華やかさが多くの人に長年愛され続ける理由です。現実の若者の恋を生き生きと描いた作品ならではの力強い躍動感があります。これが現代に至るまで観客を魅了しています。
バレエの主役ダンサーが踊る男女のペア・ダンスです。クライマックスで披露されることが多く、観客にとって最も華やかで盛り上がる瞬間です。伝統的に次の流れで構成されています。
1:アダージョ(Adagio)|男女2人で踊るゆったりとした場面。リフトやバランスで美しさを見せます。
2:ヴァリエーション(男性)|男性ダンサーのソロ。ジャンプや回転など力強い技術を披露。
3:ヴァリエーション(女性)|女性ダンサーのソロ。繊細さや安定感のある技術を見せます。
4:コーダ(Coda)|再び2人で踊る華やかな場面。速いテンポで高度なテクニックが次々と登場し、舞台は最高潮に盛り上がります。
主な登場人物
バレエ『ドン・キホーテ』には魅力的なキャラクターが多数登場します。タイトルは「ドン・キホーテ」ですが、バレエでの主役はキトリとバジルという若い恋人たちであり、ドン・キホーテ自身は2人を陰ながら助ける重要な脇役という位置付けです。
・キトリ(Kitri) – 本作のヒロインで、バルセロナの宿屋の看板娘。明るく快活な性格。父親思いだが、恋人バジルとの結婚を夢見ている。
・バジル(Basil) – キトリの恋人で床屋の青年。ユーモアと機転の利く性格の持ち主で、身分違いの恋を成就させるため奔走する。
・ロレンツォ(Lorenzo) – キトリの父で宿屋の主人。娘には金持ちと結婚して幸せになってほしいと考えており、貧しいバジルとの交際に猛反対する。
・ガマーシュ(Gamache) – キトリに言い寄る街の裕福な貴族紳士。道化じみた嫌味な人物として描かれる滑稽な求婚者。ロレンツォに気に入られている。
・ドン・キホーテ(Don Quixote) – 本名アロンソ・キハーナ。中年の郷士(貴族と庶民の中間層:小さな地主)だが騎士道物語に影響され、自らを遍歴の騎士と思い込んで旅に出た男。本作ではタイトルロール(役名が作品名となっている人物)であるものの主役ではなく、旅の途中で出会ったキトリとバジルの恋を応援する頼もしい助っ人役です。
・サンチョ・パンサ(Sancho Panza) – ドン・キホーテのお供をする従者(召使い)。食いしん坊で臆病な性格。ドン・キホーテの奇行に巻き込まれては振り回されるコミカルな存在。
・エスパーダ(Espada) – バルセロナの街で人気の闘牛士(トレアドール)の青年。華やかな闘牛士の踊りを披露し、物語にスペイン的な彩りを添える。
・メルセデス(Mercedes) – エスパーダの恋人で、美貌のストリート・ダンサー(街の踊り子)。情熱的な踊りで観客を魅了する。
・ドゥルシネア姫(Dulcinea) – ドン・キホーテの妄想の中に登場する理想の姫君。実在の人物ではなく、彼の夢の場面で妖精たちに囲まれて現れる幻影です。バレエの演出上は通常キトリ役のダンサーが二役でドゥルシネア姫を演じます。
あらすじ
物語は全3幕(プロローグ付き)で展開します。様々なバージョンがあり、演出により細部は異なりますが、大筋は共通です。
プロローグ
1600年代のスペイン。騎士道物語に心酔するドン・キホーテは、自らを勇敢な遍歴の騎士と信じ込み、従者サンチョ・パンサを連れて理想の姫「ドゥルシネア」を探す冒険の旅に出る。
第1幕:バルセロナの街の広場
にぎやかな広場で町の人々が祭りを楽しんでいる。宿屋の娘キトリは恋人バジルと幸せそうに踊っているが、父ロレンツォはキトリを金持ちのガマーシュと結婚させようとしている。キトリはガマーシュをあしらい、バジルへの愛を貫く。そこへ遍歴の騎士を名乗るドン・キホーテが町に現れ、理想の姫ドゥルシネアとキトリを重ねて勝手に感激する。やがてロレンツォはバジルを追い払い、キトリをガマーシュと結婚させようとするが、キトリとバジルは協力してその場を逃げ出す。
2014年、英国ロイヤル・バレエ団、マリアネラ・ヌニェス(アルゼンチン出身)、カルロス・アコスタ(キューバ出身)です。南米の陽気な雰囲気を持った2人の当たり役です。
東京バレエ団の昔の映像で、首藤康之さんがエスパーダ、井脇幸江さんがメルセデスを踊ります。闘牛士たちが地面に刀剣を刺すシーンがあります(4:00~)。よくある失敗で、刀剣がバタバタと倒れることも……。
第2幕:旅の途上〜夢の場〜居酒屋
キトリとバジルは町を抜け出し、ジプシーの野営地に紛れ込む。そこでドン・キホーテ一行と再会し、即興の人形劇を楽しむが、物語にのめり込みすぎたドン・キホーテ。劇中の悪役人形に真剣に立ち向かおうとし周囲を慌てさせる。さらにドン・キホーテは野営地近くの風車を巨人と勘違い。突撃して風車に絡まり、高所から落ちてしまう。気絶したドン・キホーテは、美しい妖精たちに囲まれた夢の世界で憧れのドゥルシネア姫に出会う幻想を見る(夢の場)。
ボリショイ・バレエ団プリンシパル、スヴェトラーナ・ザハーロワ(ドゥルシネア姫)が東京バレエ団と共演したときの映像です。
ドリアードの女王を踊る、パリ・オペラ座バレエ団のアニエス・ルテステュです。ドリアードとは、ギリシャ神話に登場する木の精霊のことで、本来は美男性や美少年が森に迷い込むと、美しい娘の姿で木の中に引きずり込んでしまいます。緑色の髪が特徴です。「ドン・キホーテ」において恐ろしい面はなく、森の妖精として登場。
目覚めた後、一行は再び旅を続ける。
一方、町ではキトリを追ってロレンツォとガマーシュが捜索を続け、ついに逃げるキトリとバジルが郊外の居酒屋(酒場)で捕まってしまう。絶体絶命の二人だが、そこでバジルは突然自らの胸にナイフを突き立てて自殺を図る狂言自殺に及ぶ。瀕死のバジルを見たキトリは「せめてもの望みとして死ぬ前にバジルと結婚させてほしい」と嘆願し、騒然とする中、ドン・キホーテがロレンツォを説得する。心を動かされたロレンツォは、渋々ながらキトリとバジルの結婚を許可する。途端にバジルは元気よく起き上がり、すべてが芝居だったと種明かしをするのだった(ロレンツォとガマーシュは激怒するが、ドン・キホーテが仲裁する)。
※ 構成によって順序が異なる(後述)
第3幕:結婚式の祝宴
晴れて結ばれたキトリとバジルの盛大な結婚式が町で開かれる。二人は喜びに満ちたグラン・パ・ド・ドゥ(2人の踊り)を披露し、町中が祝福の踊りに沸く。ドン・キホーテは主賓として宴を見届け、騎士としての新たな冒険を求めてサンチョと共に再び旅立つ。
タマラ・ロホ、スティーヴン・マックレーによるグラン・パ・ド・ドゥ。
こうして物語はハッピーエンドを迎えます。
原作との違い
バレエ『ドン・キホーテ』は、セルバンテスの長編小説『
原作小説の該当エピソードでは、貧しいバシリオが富豪カマーチョとキテリアの結婚式に乱入し、剣で自らを刺して狂言自殺を演じるくだりが描かれています。その場に居合わせたドン・キホーテが機転を利かせ、瀕死のバシリオの最期の願いとして二人の結婚を認めるよう説得し、結婚の誓いが済んだ途端にバシリオが「復活」して周囲を驚かせる──バレエ版のクライマックスと全く同じ展開です。このように狂言自殺で恋を成就させるアイデア自体は原作由来ですが、小説ではエピソードの一つに過ぎなかったものを、バレエではキトリとバジルの恋物語として独立した作品に仕立て直しています。さらに小説ではこの出来事の後、ドン・キホーテは旅を続け別の冒険へ移りますが、バレエでは二人の結婚式をハッピーエンドとして物語を締めくくっている点も異なります。
もう一つの大きな相違点は、ドン・キホーテの位置づけです。小説では彼自身が各章で主役となり滑稽な冒険を繰り広げますが、バレエでは上述のように主役カップルを引き立てる役回りです。そのためバレエ版『ドン・キホーテ』では、タイトルロールであるはずのドン・キホーテが舞台上に登場しない場面も多く、物語の中心はあくまでキトリとバジルに置かれています。この点は「ドン・キホーテ」という作品名から原作小説を連想すると意外に映るかもしれませんが、バレエとしては明快な恋愛喜劇にフォーカスすることでまとまりのある構成となっています。
『ドン・キホーテ』の歴史と成り立ち(プティパ原典〜現代まで)
初演プティパ版(1869年):マリウス・プティパ振付、レオン・ミンクス作曲|ロシア/ボリショイ劇場
初演(1869年)はマリウス・プティパ振付、レオン・ミンクス作曲により、1869年12月26日にモスクワのボリショイ劇場で初演されました。当時サンクトペテルブルクで名声を博していたプティパが、ボリショイ劇場からの依頼で創作しました。スペインのバルセロナを舞台に、庶民的で陽気な喜劇として作られました。物語はセルバンテスの小説『ドン・キホーテ』中の挿話(キトリ=キテリアとバジル=バシリオの恋物語)を基にしています。プティパが得意としたスペイン風の踊りを取り入れ、観客に大好評を博しました。
プティパ版(1871年):プティパ改訂振付|ロシア/マリインスキー劇場
初演の2年後(1871年)、プティパは本作を洗練させた改訂版を1871年11月にサンクトペテルブルク(マリインスキー劇場)で上演します。モスクワの大衆的で素朴な笑劇だった初版に対し、改訂版では貴族趣味の洗練を反映し、クラシック・バレエの技巧を前面に出した演出へと発展しました。具体的には、第2幕にドン・キホーテが理想の姫ドゥルシネアと出会う「夢の場」、そして第3幕(最終幕)に華麗なディヴェルティスマンとしての「結婚式の場面」が新たに追加されています。夢の場では主役キトリとドゥルシネア姫を同一のバレリーナが二役で演じる演出が導入され(初演時は別々のダンサーでした)、結婚式の場では物語と直接関係のない華やかな踊りの数々が披露されました。有名なグラン・パ・ド・ドゥ(キトリとバジルの結婚式のパ・ド・ドゥ)も、このとき初めて挿入されたもので、作品に純粋なクラシック・バレエの見せ場を加える役割を果たしました。このサンクトペテルブルク版も観客に熱狂的に迎えられ、以後『ドン・キホーテ』はロシア帝室バレエの人気レパートリーとして定着します。
古典バレエには「バレエ・ブラン(白のバレエ)」と呼ばれる群舞シーンがあり、『白鳥の湖』『ジゼル』『ラ・バヤデール』などで登場します。白い衣裳のダンサーたちが幽玄な世界をつくり出す場面です。
『ドン・キホーテ』の夢の場は、衣裳が必ずしも白で統一されていないため厳密にはバレエ・ブランではありませんが、それに匹敵する幻想性を備えています。普段は活発で快活なキトリが、ドン・キホーテの夢の中では理想化された「たおやかな姿」として登場し、まったく異なる魅力を放ちます。
ゴルスキー改訂版(1900年):アレクサンドル・ゴルスキー振付|ロシア/ボリショイ劇場
20世紀初頭(1900年)、さらに大きな転換を迎えます。1900年、ボリショイ・バレエのバレエマスターでプティパの弟子でもあったアレクサンドル・ゴルスキーが、プティパ版を大胆に改訂した新演出版を発表しました。ゴルスキーは当時流行していたスタニスラフスキー・システムの影響を受け、踊りの形式美より演劇性と自然さを重視しました。
役をリアルに生きるための演技理論です。台本が与える事実を土台にしつつ、台本から外れない範囲で空想の設定を加えて人物像を深掘りします。「もし自分がその立場なら?」と想像し、舞台上でどう行動するか、どう振る舞うかを反映させていきます。
ゴルスキー版では群舞を含むすべてのダンサーに生き生きとしたリアルな演技が求められます。例えば第1幕の広場の場面では街の群衆一人ひとりが役柄に応じた個性的な振る舞いを見せるよう工夫されています。振付構成も見直され、プティパ版で多用されていた左右対称のフォーメーションを避け、各ダンサーやキャラクターが際立つよう再構成されました。さらに音楽面でも、ミンクスの原曲に他の作曲家による曲を追加し、舞台美術も当時の時代考証に基づいた写実的なものに改めています。
| 追加楽曲 | 作曲者 | 挿入された場面・役割 |
|---|---|---|
| ドリアードの女王のヴァリエーション | アントン・シモン | 「夢の場」で登場するドリアード(森の精)の女王のヴァリエーション。ゴルスキーがこのキャラクターを導入した際に追加された。 |
| アムールのヴァリエーション | バルミン(元は『パキータ』用) | 「夢の場」のアムール(キューピット:愛の精霊)のヴァリエーションとして挿入。 |
| ドゥルシネアのヴァリエーション | リッカルド・ドリゴ | 「夢の場」のキトリ/ドゥルシネア二役の場面に挿入。クシェシンスカヤ(キトリ/ドゥルシネア役)のために作曲された。 |
ゴルスキーの大胆な改訂は師であるプティパの激怒を買ったと言われます。1902年にサンクトペテルブルクで上演した際、リハーサルを見たプティパは自作が全面的に改変されていることに憤慨したという逸話も残っています。しかし結果的にゴルスキー版『ドン・キホーテ』は成功を収め、現在上演されている本作のほとんどはこのゴルスキー版を基にしていますソ連時代から各国へ伝播し、現在ほとんどの上演で振付クレジットに「プティパ/ゴルスキー」と記載されています。日本初演(1965年:谷桃子バレエ団)もメッセレルの指導により上演されました。
西側への紹介と世界的普及
『ドン・キホーテ』は20世紀半ばまでソ連を中心に上演されていましたが、西側で全幕が紹介されたのは意外にも遅く、1962年、ロンドンのランベール・バレエ団(後のイングリッシュ・ナショナル・バレエ団の前身)が西側初の全幕上演を行ったとされています。その後、1960年代以降にソ連から亡命したスター・ダンサーたちが次々に西側で『ドン・キホーテ』を振付・上演し、一気に世界的に知られるところとなりました。
代表的なのがルドルフ・ヌレエフとミハイル・バリシニコフで、彼らはそれぞれ独自の演出版を発表し(後述)、本作の魅力を欧米の観客に強烈にアピールしました。以降、『ドン・キホーテ』はアメリカン・バレエ・シアター(ABT)やパリ・オペラ座バレエ団など主要バレエ団の定番レパートリーとなり、日本を含む世界中で愛される古典バレエの一つとなっています。
主要な振付版の系譜(プティパ、ゴルスキー、ヌレエフ、アコスタ他)
上記のような歴史を経て、『ドン・キホーテ』には数多くの振付家・演出家による改訂版が存在します。プティパ原典からゴルスキー版を経て、20世紀以降各振付家が作品を発展させていきました。
| 振付家・版 | 初演(バレエ団・都市) | 特徴 |
|---|---|---|
| マリウス・プティパ | ボリショイ・バレエ団/モスクワ(1869) マリインスキー・バレエ団/ペテルブルク(1871) |
喜劇的 → クラシック技巧追加、夢の場・結婚式を導入 |
| アレクサンドル・ゴルスキー | ボリショイ劇場/モスクワ(1900) | 演劇性・自然な群舞、追加音楽・写実的美術 |
| ルドルフ・ヌレエフ | ウィーン国立歌劇場バレエ/ウィーン(1966) パリ・オペラ座バレエ団/パリ(1981) |
男性ダンサーのテクニック強化 華やかなスペイン風 |
| ミハイル・バリシニコフ | アメリカン・バレエ・シアター(ABT)/ニューヨーク(1978) | コミカルでスピード感、映像化で普及 |
| ケヴィン・マッケンジー | アメリカン・バレエ・シアター(ABT)/ニューヨーク(1995) | 豪華版、ABT現行レパートリー |
| アレクセイ・ファジェーチェフ | ボリショイ・バレエ団/モスクワ(1999) | 古典美+現代的演出、新国立劇場版にも採用 |
| カルロス・アコスタ | 英国ロイヤル・バレエ団/ロンドン(2013) | 伝統+声やギター演出、21世紀の新定番 |
ヌレエフ版以降を補足説明します。
ルドルフ・ヌレエフ版
1966年|ウィーン国立歌劇場バレエ(初演)
1981年|パリ・オペラ座バレエ団(改訂版初演)
ソ連から亡命した伝説的ダンサーが西側にもたらした画期的なプロダクションです。ヌレエフ版は超絶技巧をふんだんに盛り込んだ華やかな振付が特徴で、特に男性主役バジルの見せ場を大幅に強化しました。スペイン風の豪華な衣装・美術も相まって、全編がダンスの祭典のような仕上がりです。パリ・オペラ座バレエ団の定番として現在も上演されています。他にもウィーン国立バレエ、ミラノ・スカラ座バレエ団、オーストラリア・バレエ団など世界各地でレパートリーに入っています。ヌレエフ自ら出演・監督した映画版(1973年)でも有名で、西側における『ドン・キホーテ』普及に貢献しました。
ミハイル・バリシニコフ版
1978年|アメリカン・バレエ・シアター(ABT)初演
名ダンサー・バリシニコフ(愛称ミーシャ)が、自らバジルを踊りつつABT芸術監督として振付・演出したバージョンです。高度なテクニック、コミカルな演技、スピーディーな展開が持ち味で、「ミーシャといえばドンキ」と言われるほど人気を博しました。1983年には主演・演出・振付を兼ねた映像作品も制作され、世界的に広く親しまれています。現在も販売されています。ABTの代表的レパートリーとして長年上演され、1980年代以降各国のバレエ団にも影響を与えました。現在ABTでは後述のマッケンジー版(1995年)に置き換えられていますが、バリシニコフ版で確立した演出(スピード感ある展開や振付の工夫)が受け継がれています。
未だに衝撃を受けるミハイル・バリシニコフのバジルとシンシア・ハーヴェイのキトリです。
とにかくミハイル・バリシニコフが輝いています。
ケヴィン・マッケンジー/スーザン・ジョーンズ版
1995年|ABT初演
ABT芸術監督マッケンジーとバレエ・ミストレスのジョーンズにより、バリシニコフ版に替わる新プロダクションとして制作。プティパ/ゴルスキー原典に立ち返りつつ、装置や演出を一新した豪華で安定感のある版と評されています。
アレクセイ・ファジェーチェフ版
1999年|ボリショイ劇場初演
ボリショイ出身の振付家ファジェーチェフが、芸術監督在任中に手掛けたバージョン。プティパ/ゴルスキー版を基に古典美と現代的演出を融合した壮麗な舞台で、往年のソ連版に代わる新定番となりました。日本の新国立劇場バレエ団もファジェーチェフを招聘し、1999年にこの版を初演。以降も再演を重ねていて、新国立劇場のスタンダードとなっています。
カルロス・アコスタ版
2013年|英国ロイヤル・バレエ初演
キューバ出身の名ダンサー、カルロス・アコスタがロイヤル・バレエ在籍時に振付した近年のバージョン。伝統的なプティパ系の振付を基本にしつつ、ダンサーが舞台上で声を発する演出やジプシーの場面で実際にギタリストが登場するなどユニークな工夫が盛り込まれています。映像化もされ高評です。近年では振付者アコスタ自身が芸術監督を務めるバーミンガム・ロイヤルバレエなどでも再演されており、21世紀の新たな定番演出の一つとなりつつあります。
※上記のほか、ソ連時代にはフョードル・ロプホフ版(1923年)やロスチスラフ・ザハロフ版(1940年)なども制作されています。またプティパ/ゴルスキー版とは異なるアプローチの作品として、ニネット・ド・ヴァロワ版(1950年)やジョージ・バランシン版(1965年)など別楽曲・別振付による『ドン・キホーテ』も発表されましたが、これらは現在ほとんど上演されておらず、一般的にはプティパ系統の作品が主流です。
2系統あるストーリー
クライマックスであるバジルの狂言自殺(仮死)の場面は、バージョンによって登場する順序(幕・場面構成)が2パターン存在します。
パターンA:居酒屋(バジルの狂言自殺)→ ジプシーの野営地 → ドン・キホーテの夢
狂言自殺の場面が物語中盤(第2幕の前半)に位置し、その後にドン・キホーテの風車との戦いから夢の場面へと続く形です。この場合、バジルが一度息絶えたふりをした後で物語が一時中断し、夢やさまよいの場面を経てから結婚式へと至るため、物語の山場(恋人たちの結婚許し)がやや早めに来る構成です。伝統的なロシア上演の系統ではこのパターンが見られ、例えば新国立劇場バレエ団が採用するファジェーチェフ版はこちらにあたります。
パターンB:ジプシーの野営地 → 夢の場 → 居酒屋(狂言自殺)
狂言自殺の場面が物語後半(第2幕の後半または第3幕)に置かれ、恋人たちの駆け落ち → 風車での乱闘 → ドン・キホーテの夢を経て、最後に居酒屋で父親を説得するクライマックスを迎える形です。こちらは物語が時系列どおり一直線に進行します。終盤に向けて盛り上がる構成で、ヌレエフ版やバリシニコフ版がこのパターンを採用しています。多くの欧米のバレエ団が上演する版も基本的にこちらの流れになっています。
これら2つの系統は、一見すると物語の順序を入れ替えただけにも思えますが、その演出的意図には違いがうかがえます。パターンA(狂言自殺→夢)は、プティパが1871年の改訂で取った構成に近いと考えられます。プティパはサンクトペテルブルク版で「夢の場」と「結婚式の場」を新設しましたが、これらは物語の本筋(キトリとバジルの駆け落ちと和解)とは直接関係のないクラシック・バレエの見せ場として追加されたものでした。そのため、物語上の決着がついた後にも踊り主体の場面が続く構成になっており、貴族趣味の観客を満足させるために物語のピークを途中に置いてでも華麗な舞踊シーンを挿入したと言えます。狂言自殺の場面を早めに配置することで、第3幕の結婚式を純粋な祝祭的ディヴェルティスマン(本筋の物語進行には直接関わらない、踊りだけを楽しむためのシーン)としてたっぷり見せる意図がありました。
一方、パターンB(夢→狂言自殺)は、物語の整合性やドラマの盛り上がりを重視し再構成したと考えられます。ヌレエフやバリシニコフといった演出家・振付家たちは、西側の観客にも分かりやすく楽しめるよう物語を洗練しようとしました。その結果、物語のクライマックスである狂言自殺による大団円を終盤に据え、夢の場は物語の途中(バジルたちが逃避行のさなかに見る幻想)として組み込みました。この構成では、観客は最後まで「キトリとバジルの恋の行方」をハラハラ見守り、居酒屋での痛快な逆転劇でカタルシス(心が動かされ、すっきりと解放される体験)を得て一気に結末まで駆け抜けることができます。いわばドラマの起伏を最大化するための演出意図が反映されています。
DVDで楽しむ『ドン・キホーテ』オススメ作品
『ドン・キホーテ』は、その明るさと超絶技巧ゆえに、バレエ界で特別な位置を占めています。日本でも、3年に一度開催される「世界バレエフェスティバル」において、必ずフィナーレを飾る作品として選ばれてきました。世界最高峰のダンサーたちがこの舞台で披露するグラン・パ・ド・ドゥは、観客にとって最大の楽しみのひとつです。
まさに『ドン・キホーテ』は、初心者から愛好家まで誰もが楽しめるバレエです。
・ルドルフ・ヌレエフ版
3,000円ほど。本人が踊っています。
・アレクセイ・ファジェーチェフ版
4,200円ほど。スヴェトラーナ・ザハロワが新国立劇場バレエ団に客演しました。
・カルロス・アコスタ版
6000円ほど。高田茜さん、アレクサンダー・キャンベル主演です。
4,000円ほど。マヤラ・マグリ、マシュー・ボール主演です。
おまけ:日本人ダンサーの世界的活躍
バジルのヴァリエーションは、超絶技巧の見せ場として知られています。こちらは世界の舞台で活躍する日本人ダンサー、三宅啄未(Takumi Miyake)さんによるリハーサル。アメリカン・バレエ・シアター所属。世界トップレベルの技術をぜひご覧ください。
以上、バレエ「ドン・キホーテ」の作品解説でした。ありがとうございました。
バレエ作品に関してはこちらにまとめています。ぜひご覧ください。




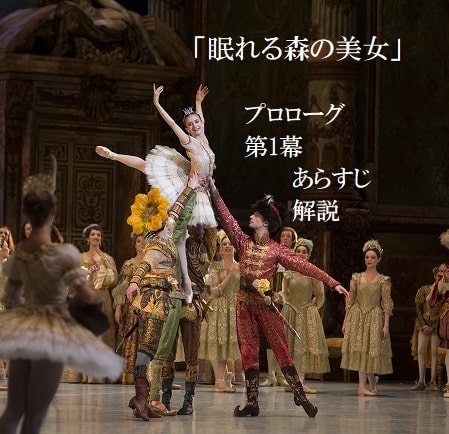
.png)

