
- 基礎知識が一気にわかる:歴史・振付・音楽、ウィリ伝説と物語
- あらすじと世界観:悲劇と赦しの流れを整理
- 見どころの解説:主役、群舞、音楽の聴きどころ
『ジゼル』は19世紀の初演以来ずっと演じ続けられている「知っていて損なし」の定番作品で、日本でも根強い人気があります。
物語には、結婚前に亡くなった娘たち(精霊ウィリ)が支配する深い森が登場し、精霊の世界を幻想的に描き出します。
今回は、『ジゼル』の作品解説です。前半は、初めての方でもこれだけ知っていれば楽しめる基礎知識やあらすじを。後半では、歴史的背景や技術的なポイントを深掘りして解説します。
元劇団四季、テーマパークダンサー。舞台、特にバレエを観に行くのが大好きで、年間100公演観に行った記録があります。
※ 5分ほどで読み終わります。
基本情報
『ジゼル』は、美しくも哀しい音楽、その芸術性と演劇性の高さから、チャイコフスキー三大バレエ(『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』)に匹敵する人気を誇り、世界中のバレエ団で頻繁に上演されています。
幻想的な白いロマンティック・チュチュ姿(薄いチュールを重ねたスカート:丈は膝下〜足首あたり)の精霊が登場するバレエです。精霊と聞くと、静かで儚いイメージに思えますが、驚くほど力強く攻撃的に踊ります。純白の群舞が整然と並ぶ美しさ。その裏に潜む怨念が観客を魅了します。
主な登場人物
主役のジゼルとアルブレヒトには高度な技術と豊かな演技力が求められ、歴代の名だたるバレエダンサーが挑んできた作品です。
あらすじ(全2幕)
中世ドイツのライン川近くとされる村。第1幕は牧歌的な農村の広場が舞台で、日の光あふれる快活な収穫祭が開かれています。
第1幕:村の娘の悲劇
ぶどうの収穫祭でにぎわう田舎の村。病弱だが踊り好きな美しい村娘ジゼルは、恋人のアルブレヒトと幸せに過ごしています。ただしアルブレヒトは身分を隠して「ロイス」という偽名を使っています。実は近くの領主であるシレジア公爵アルブレヒト本人でした。彼には婚約者のバチルド姫がおり、身分違いの恋を楽しんでいたのです。
※ アリーナ・コジョカルのジゼルです。
ジゼルに想いを寄せる森番ヒラリオンは、アルブレヒトの正体に勘付きます。そして、村を訪れたバチルド姫を含め村人たちが集まる前で、ヒラリオンがアルブレヒトの身分を暴露します。貴族であることを否定できなくなったアルブレヒト。真実を知ったジゼルは心神喪失に陥り、狂乱の末に息絶えてしまいます。
【独り言】 幕が閉まった直後、拍手に応えて「カーテンコール」が起こることがあります。とはいっても、通常の華やかな挨拶ではありません。幕が閉じた時と同じ「全員が絶望して凍りついたポーズ(フリーズ)」のまま再度幕が開き、そのまままた静かに閉じるという演出です。個人的にはダンサーの人たち大変だな、という感情が勝ってしまい少し苦手な演出です。
第2幕:精霊たちの森と赦し
真夜中の深い森の中。人里離れた場所にジゼルの墓がひっそりと建てられています。深夜になると精霊ウィリが出現します。ウィリとは結婚を目前にして命を落とした花嫁たちの亡霊で、女王ミルタが支配します。強い未練から成仏できずに夜な夜な墓場をさまよっています。生前に果たせなかった踊りの喜びを味わうために、若い男性を見つけては誘惑し、明け方まで踊らせて命を奪うといわれます。ジゼルの墓の前にウィリたちが現れます。
墓参りに来たヒラリオン、ウィリたちに捕らえられ命を落としてしまいます。
次に現れたのはアルブレヒトです。彼もまたウィリたちに取り囲まれ、夜明けまで容赦なく踊り続けることを強いられます。アルブレヒトが力尽きそうになったとき、亡霊となったジゼルが現れ、必死に彼をかばいます。ジゼルの愛は死を超えても純真です。
※ 当たり役として知られたアレッサンドラ・フェリ(アメリカン・バレエ・シアター)、マニュエル・ルグリ(パリ・オペラ座バレエ団)です。
やがて遠くで朝を告げる鐘が鳴ると、復讐に燃えるウィリたちも力を失い森の闇へ消えていきます。ミルタたちが去るとジゼルも静かに成仏し、墓前には命拾いしたアルブレヒトだけが残されます。深い悔恨と愛惜の念を胸に、ひとり夜明けの森に立ち尽くすのでした。
見どころ
第2幕後半、ジゼルとアルブレヒトが再会して踊るパ・ド・ドゥを紹介します。ジゼルは亡霊となった身でアルブレヒトを支え、愛の力で寄り添います。アルブレヒトは罪の意識と愛情の中で苦悩しながらも、ジゼルの優しさに触れて浄化されていきます。
先程も映像で紹介しましたが、このパ・ド・ドゥではジゼル役の高度なアダージョ技術(ゆっくりした動きのバランス)と、アルブレヒト役のリフトやサポートの巧みさが試されます。ガラ公演でも頻繁に上演される人気のパ・ド・ドゥです。
※ パリ・オペラ座バレエ団より、シルヴィ・ギエムと、ローラン・イレールです。
アルブレヒトは次第に力尽き、精魂を使い果たしていきます。アントルシャ・シス(entrechat six:足を3回交差)を連続で跳ぶという高難易度の振付があり、男性ダンサーの体力の見せ場となっています。これはウィリたちに踊らされる様子を象徴する振り付けで、名だたるダンサーたちがこの場面で観客を沸かせてきました。
※ ボリショイ・バレエ団より、ドミトリー・スミレフスキーです。
ベテランになると、回数を早く切り上げることがあり、おやっ?となる場面です。
オススメDVD
『ジゼル』はDVD化も多くオススメがたくさんあります。
英国ロイヤル・バレエ団
まずは英国ロイヤル・バレエ団より。アリーナ・コジョカルとヨハン・コボー主演です。
アリーナ・コジョカルがあまりにハマっています。僕も生で観たことありますが、いつも素晴らしいです。
パリ・オペラ座バレエ団
次はパリ・オペラ座バレエ団より、レティシア・プジョルとニコラ・ル・リッシュ主演です。
ニコラ・ル・リッシュの演技がとくにオススメです。
ボリショイ・バレエ団
最後はボリショイ・バレエ団より、スヴェトラーナ・ルンキナ、ドミトリー・グダノフ主演です。
ボリショイ・バレエ団の持つ、重々しい雰囲気はやはり素晴らしいです。
【後半】詳細パート:もっと深く知る『ジゼル』の世界
ここからはさらに詳しく知りたい方に向けて『ジゼル』を深掘りしていきます。歴史的な背景を含め、作品の解釈を広げるマニアックな情報をお届けします。
第1幕の見どころ:狂乱の場
第1幕は何と言っても、裏切りを知ったジゼルが心を病んで死に至る「狂乱の場」が圧巻です。純真だった村娘が絶望に沈み狂気を爆発させる演技は、表現力を試される最大の山場です。「愛のテーマ」が不安定な音程で繰り返し演奏され、狂気と哀しみを表現します。ジゼルが幼い子供のように幻覚を見てアルブレヒトと踊ろうとする場面から、正気に戻る場面を通過、そして息絶える瞬間まで、観客は手に汗握る緊張感に包まれます。
この狂乱の場を演じるダンサーには、凄まじい狂気と同時に、極めて高い冷静さが求められます。この場面で特に注目したいポイントが「髪留め」の扱いです。狂乱の場に入る直前、ジゼルは自らの手で髪留めを外します。髪を振り乱し、バサバサさせることで視覚的な狂気が加速していきます。ですが、実はこの動作は難易度が高いです。バレエの舞台では、激しい回転の最中に髪が崩れないよう、通常は信じられないほどガッチリと髪を固定します。
しかし、ジゼルという役においてはあえてその固定を解かなければなりません。この成功率が意外に低く、片方だけ外れずに残ってしまうこともよく起こります。髪の状態が不自然だと観客の集中を削いでしまうため、この細かな所作を完璧にこなし、美しく髪を解いて狂気を表現しきったダンサーには、さらなる賞賛の拍手を送りたくなります。
※ スカラ座バレエ団より、アレッサンドラ・フェリ(ジゼル)、マッシモ・ムッル(アルブレヒト)です。
病弱とテクニックの矛盾
ジゼルは「心臓が弱い病弱な娘」という設定ですが、第1幕のバリエーションで高度なテクニックを全力で披露しようとすると、どうしても動きがパワフルで生き生きしてしまいます。あまりに健康的すぎると役柄の説得力が崩れてしまうため、超絶技巧をこなしながらも、ふとした瞬間に儚さを感じさせる表現力が求められます。両立しているダンサーに出会えると感動が倍増します。
ロマンティック・バレエ
『ジゼル』は、19世紀前半のロマンティック・バレエを代表する作品です。
19世紀前半(おもに1830〜1850年代)に流行したバレエの様式。「日常」と「夢の世界」を行き来しながら、手の届かない女性像(妖精・精霊・亡霊)を描きます。パリ・オペラ座を中心に発展し、その後ロンドンやサンクトペテルブルクへ広がりました。
代表作:
・『ラ・シルフィード』(1832) 振付:フィリッポ・タリオーニ|ロマン派の幕開け
・『ジゼル』(1841) 振付:コラーリ/ペロー、音楽:アダン|第2幕が様式の典型
・『エスメラルダ』(1844) 振付:ペロー|ロマン派のドラマ性を強調
・『パ・ド・カトル』(1845) 振付:ペロー|当時の四大バレエダンサーの競演
第1幕では明るい現世(農村)、第2幕では神秘的な異界(夜の森)が描かれます。この現実世界と幻想世界の対比こそがロマンティック・バレエの型であり、同時代の『ラ・シルフィード』と並んで『ジゼル』はその典型例となりました。
トウ・シューズ
1832年『ラ・シルフィード』で、マリー・タリオーニが見せた軽やかなつま先の動きと、ふわりと霧のように揺れるロマンティック・チュチュは、舞台上に「重力を忘れる」視覚を生み、いわゆるロマンティック・バレエの象徴となります。ここから、妖精や精霊といった「この世ならぬ存在」を主役に据える美学が確立していきました。
この浮遊感を支えたのが、「トウ・シューズ(=ポイント・シューズ/仏語:ポワント)」です。つま先側の硬いボックス(箱型)が指先を包み、足裏の芯材(シャンク)が甲を支える構造です。これらが、つま先立ちを可能にします。
トウ・シューズは誰でもすぐに履けるものではありません。開始の目安はしばしば「12歳以降」とされますが、年齢だけでなく、足首の可動域や足のアライメント(姿勢)、体幹の安定性、日頃のレッスン量などの条件がそろって初めて先生から許可されます。
トウ・シューズと身体づくりが噛み合うと、観客には舞台上のダンサーが「人ならざる存在」に見えてきます。その錯覚を支えるのがロマンティック・チュチュと繊細なトウ・シューズです。パリ・オペラ座バレエ団も「第2幕のロマンティック・チュチュとポワントが精霊の不思議な雰囲気を本質的に生み出す」と説明しています。
さらに、足音を消す工夫も現実に引き戻さないための重要なポイントです。というのも普段トウ・シューズは舞台上で乾いた「カンッ!!」という音が響くことがあります。トウ・シューズを柔らかくする加工を行い、舞台の床に当たる音をできるだけ抑えるダンサーもいるほどです。
ウィリ伝説の解釈と背景
「ウィリ(Wili)」は元々中央ヨーロッパやスラヴ圏の伝承に登場する女性の亡霊のことで、生前に結婚できずに死んだ花嫁たちの霊魂を指します。
台本を書いたテオフィル・ゴーティエは、ドイツの詩人ハインリヒ・ハイネの著書『ドイツ論(精霊物語)』の中で語られていた「無慈悲にワルツを踊るウィリたち」の伝説から着想を得て、台本を生み出しました。劇中でジゼルの母ベルタが語るように、ウィリたちは夜な夜な墓場に集い、生前の恨みから森に迷い込んだ若い男性を見つけては夜明けまで踊らせ殺してしまいます。
踊り続けること自体、ウィリたちが生涯で満たされなかった肉体的欲望のメタファー(暗喩)とも解釈されます。こうした伝説上の女性たちはフランス語で「精霊」と呼ばれますが、その所業はまるで妖怪や雪女のように恐ろしく、男性にとっては脅威です。
森の奥深くにウィリたちの墓がある設定も、中世ヨーロッパで異端者や自殺者が共同墓地に葬られず人里離れた森に埋められた史実と結びついています。『ジゼル』の物語は、このウィリ伝説に典型的なロマン主義の美学(現実と異界、生と死の対比)を融合させ、人間の愛と赦しを描いています。
第2幕:バレエブラン
第2幕は、白いチュチュに身を包んだウィリたちの群舞が最大の見せどころです。月光の下、一糸乱れぬ隊列で繰り広げる精霊たちの踊りは幻想そのもの。「バレエ・ブラン」の名にふさわしい純白の美しさと統制の取れた動きと照明の力で世界に入り込んでしまいます。
バレエ・ブラン(白のバレエ):白いチュチュを纏った精霊たちの群舞による幻想的な場面を指します。 『ジゼル』第2幕のように、純白の美しさと統制された動きで「この世ならぬ存在」の世界を幻想的に描き出します。
中でも有名なのが、ウィリたちが長いチュチュの裾をふわりと翻しながら連続でアラベスクを行う動きです。まるで幽霊が宙を浮遊しているかのような錯覚すら起こさせます。観劇後、小さなバレエダンサーたちがよくマネをしているのを見かけるくらい印象に残ります。
これに対しミルタは強靭なテクニックを要する難役です。ミルタは豪快な大跳躍(グラン・ジュテ)を次々と披露し、素早い動きで森を駆け巡ります。激しい振付にもかかわらず、常に冷淡で威厳ある表情です。この「激情を内に秘めた静」と「踊りの動的な激しさ」の両立がミルタ役の醍醐味であり、見応えとなっています。
※ パリ・オペラ座バレエ団より、ミルタ役はマリ=アニエス・ジロです。
やがて夜明けの鐘の音とともにウィリたちが去り、ジゼルとアルブレヒトが別れる瞬間、再び静かな愛のテーマが流れます。ジゼルがアルブレヒトにそっと寄り添い、消えゆく姿……。アルブレヒトが独り残され絶望するラストの余韻まで含め、第2幕は音楽・舞踊・ドラマが一体となって観客の心を揺さぶります。
名ダンサーたち
『ジゼル』は古今東西のトップダンサーが挑んできた特別な演目です。初演でジゼルを踊ったカルロッタ・グリジは当時19歳。彼女の才能に惚れ込んだ作家ゴーティエがこの作品を創作したとも言われ、まさに彼女のための役でした。グリジのジゼルは愛らしさと狂気を見事に演じ分け、19世紀パリの観衆を熱狂させたと伝えられています。
その後も伝説的解釈が次々と生まれました。ロシアではガリーナ・ウラノワが1950年代にこの役で世界的評価を受け、「ジゼルの化身」と称えられました。
英国ではマーゴ・フォンテインが繊細で気品あるジゼルを演じ、ルドルフ・ヌレエフとのペアで名舞台を残しています。
キューバのアリシア・アロンソは、若干22歳で代役からジゼル役を掴み取りスターに上り詰めた逸話が有名です。1943年、ニューヨークのバレエ・シアター公演で主演のアリシア・マルコワが病に倒れた際、無名だったアロンソが大抜擢されました。アロンソは密かに全幕を学んでおり、見事な出来栄えで観客を魅了しました。この舞台を機に「20世紀最高のジゼル」の一人と謳われ、以後何十年にもわたり彼女は視力障害を抱えながらもジゼルを踊り続けました。自身の振付バージョンも編み出し、故国キューバやパリ・オペラ座にも伝承しています。
役の解釈
こうした逸話は『ジゼル』という役がいかにダンサーにとって特別であるかを物語っています。ジゼルは一人のダンサーの中に少女、狂女、精霊という三つの姿を要求する難役です。そのため解釈も踊り手によって微妙に異なります。時代時代のダンサーそれぞれの演技プランが作品に奥行きを与えてきました。
例えば、第1幕のジゼルを「心臓の弱い少女」として演じるか、「無邪気だが情熱を秘めている娘」として演じるかで印象が変わります。狂乱の場面での細かな所作ひとつ(恋人と踊った思い出を幻影と踊るかのように再現する仕草など)に至るまで、各ダンサーが工夫を凝らしています。歴史的に見ても、アンナ・パヴロワ、オリガ・スペシフツェワ、アリーナ・コジョカル、スヴェトラーナ・ザハーロワなど数々の名演が残っています。
アルブレヒト役についても、第1幕で「ジゼルを本気で愛している純粋な青年」と捉えるか、「ほんの遊びで村娘に手を出した貴公子」と捉えるかで役作りは両極に振れます。
このように、名演の裏には綿密な演技プランがあります。各々の解釈の違いを楽しめるのも『ジゼル』鑑賞の醍醐味です。
第1幕:ニュースターたち
第1幕前半、男女ソリスト2名が見せるパ・ド・ドゥは、コンクール演目にも選ばれる曲で、女性ヴァリアシオンの高速なピルエット、男性の軽快な跳躍など見せ場が続きます。初演前に急遽追加されたナンバーですが、その完成度の高さから現在では本編に欠かせない人気シーンです。プリンシパル候補の若手ダンサーが配役されるのも見どころです。
※ 英国ロイヤル・バレエ団より、変則的なパ・ド・シス(6人の踊り)です。2026年現在、このうち3人がプリンシパルとして活躍しています。
作品の上演史とバージョンの違い
パリで誕生してからロシアに渡り、世界に広がった歴史があります。
初演と大成功
1841年パリ初演の『ジゼル、またはウィリたち』は大成功を収めました。主演のカルロッタ・グリジは絶賛され、以後しばらくパリ・オペラ座でグリジとリュシアン・プティパ(マリウス・プティパの兄)主演で再演が続きます。しかし、ロマン主義バレエの衰退により、1868年を最後にオペラ座での上演は途絶えてしまいました。
ロシアでの継承
一方、フランスからロシアに伝わった『ジゼル』は1842年にペテルブルクで初演され、以降ロシア帝国で受け継がれていきました。振付家ジュール・ペロー自身が1848年にボリショイ劇場のバレエマスターに就任し、ロシア版『ジゼル』を改訂し、パリのオリジナル版に近づける試みもありました。19世紀後半までロシア各地で上演が重ねられ、当時新進ダンサーで、後に振付師となるマリウス・プティパ自らアルブレヒト役を踊っています。
決定版の誕生は、プティパが振付家として改訂上演を任されてからです。1884年と1887年、さらに1899年と1903年にプティパは帝政ロシアのマリインスキー劇場で『ジゼル』を改訂上演しました。1884年の改訂では第1幕に新たなグラン・パ・ド・ドゥが追加され、第2幕の群舞やコーダも拡充されました。このプティパ版が現在上演されている『ジゼル』の基本形で、20世紀以降の上演はほぼすべてプティパ版に準拠しています。なお、1884年プティパ版でレオン・ミンクスが作曲したパ・ド・ドゥですが、現在は上演に含まれないことが多いものの楽譜自体は残されています。
西欧での復活上演
ロシアで磨かれた『ジゼル』は、20世紀に入ると再び西欧の舞台に姿を現します。1910年、ディアギレフ率いるバレエ・リュスがパリ・オペラ座で『ジゼル』を上演し(主演:タマラ・カルサヴィナ&ワスラフ・ニジンスキー)、1924年にはパリ・オペラ座バレエ団がプティパ版を逆輸入して本格的にレパートリーとして復活します。以降、フランスで定番のレパートリーとなり、20世紀後半までに世界中の主要バレエ団へと伝わっていきます。
例えばイギリスでは、1934年にロンドンのヴィック・ウェルズ・バレエ団(現ロイヤル・バレエ)の創成期にニコライ・セルゲイエフがロシアから持ち出した舞踊譜(バレエの楽譜のようなもの)を元に初演し、当時22歳のアリシア・マルコワが英国初のジゼルを踊りました。以後も英国ではマーゴ・フォンテインらが当たり役とし、英国ロイヤル・バレエ団のピーター・ライト(1965年初演)が演出を手掛けるなど独自の伝統を築いています。
アメリカでは、キューバ出身のアリシア・アロンソが在籍したバレエ・シアター(現アメリカン・バレエ・シアター:ABT)で人気演目となりました。ABTでは現在もケヴィン・マッケンジー振付のプティパ系統が上演されています。同カンパニーには1940年代にアロンソ自ら改訂した版もあります。
その他、ソ連時代のレオニード・ラヴロフスキー版(1944年初演)など各国で多彩な演出が生まれました。
近年では、マッツ・エック版(1982年初演、舞台を精神病院に翻案)や、クレオール・ジゼル(1984年、アフリカ系コミュニティに置き換え)、アクラム・カーン版(2016年、移民労働者の近現代劇)など現代的に再解釈した異色の『ジゼル』も発表されています。
物語結末の違い
伝統的なクラシック版にも細かな違いがあります。
初演版では、結末にバチルド姫が再登場しました。ジゼルがアルブレヒトに「バチルド姫のもとへ帰って」と彼を託して消える演出がありました。しかし現在はこの場面は省かれ、バチルド姫は登場しません。現在は、アルブレヒトがひとり残り、後悔に打ちひしがれるエンディングが主流です。この改変によって、アルブレヒトのジゼルに対する深い愛が強調されるようになっています。
またジゼルの死因も解釈が分かれる点で、「ジゼルが剣で自害する」バージョンと、「心臓発作で倒れる」バージョンがあります。自害版の場合は前述のとおりジゼルが森に葬られる理由づけが明確になり、アルブレヒトの剣(紋章入り)への伏線も活かされる一方、心臓発作版の場合はより純粋な悲劇性が際立つという違いがあります。
各国の伝統や演出家の意図によって異なりますが、いずれにせよ物語の大筋に変わりはありません。
音楽の特徴と魅力
作曲者アドルフ・アダン(1803年~1856年)は、『ジゼル』でロマンティック・バレエ音楽の名作を残しました。ライトモチーフ(登場人物の性格、感情を表現する音楽のフレーズ:作中に繰り返し登場)の効果的な使用が特徴で、登場人物や出来事を象徴する特定の主題・旋律が作品中何度も繰り返されます。例えば、序幕でジゼルとアルブレヒトが幸せに踊る場面の旋律は、後の狂乱の場面で不安を帯びて再現されます。
またベルタが語るウィリ伝説の場面や、ジゼルが正気を失う場面、第2幕でウィリたちが出現する場面では、いずれも共通の「ウィリの主題」が低音で流れ、物語全体に不吉な統一感を与えています。これらのライトモチーフによって音楽とドラマが密接に結びつき、観客は旋律から登場人物の心情や状況の変化を感じ取れるようになっています。
音楽の聞きどころとしては、ジゼルとアルブレヒトの愛のテーマの美しさがまず挙げられます。第1幕の出会いから二人のパ・ド・ドゥで流れるこの甘い旋律は、第2幕のラストでジゼルがアルブレヒトを赦す場面にも静かに回帰し、観客の胸に余韻を残します。
また、第2幕序盤、ミルタがウィリたちを従えて登場する場面の音楽は冷たく厳かな空気感で支配し、続くウィリたちの群舞(バレエ・ブラン)は軽やかなリズムに乗せて不気味な美しさを醸し出します。これらの旋律は一度聞けば耳に残る印象的なものばかりで、ロマンティック・バレエ音楽の傑作と評される理由です。物語展開と踊りを見事に融合させる機能性と叙情性に富んでいて、後の作曲家(レオン・ミンクスやチャイコフスキーら)にも影響を与えました。
アダンの音楽はメロディアスで分かりやすく、バレエ音楽として踊りやすいリズム感も兼ね備えています。序曲から第1幕に登場する明朗なワルツや、「ペザント(村人)・パ・ド・ドゥ」の華やかな曲想は農村の賑わいを描きます。第2幕で一転する静謐な弦楽のハーモニーや神秘的なオーボエの旋律は夜の森の冷気と幽玄さを表現しています。
なお、第1幕で踊られるペザント・パ・ド・ドゥの音楽は一部アダンの作曲ではなく、作曲家フリードリヒ・ブルグミュラーが提供した8小節ほどの旋律が含まれます。これは初演時、あるダンサーのソロのため急遽差し込まれた曲と言われています。またアダンは他にも、別の作曲家の楽曲から短いフレーズを引用して用いる遊び心も見せました(※ウェーバー作曲のオペラ『オイリアンテ』からの引用が数小節含まれることが確認されています)。
こうした手法も当時のバレエ音楽では珍しくなく、限られた作曲期間で多彩な場面に音楽を当てはめる工夫であったと考えられます。アダン自身は後年の回想録で「3週間でこの大作を書き上げた」と述べていますが、実際にはオーケストラ化(管弦楽化)を含めもっと時間を要したようです。それでも短期間でこれだけ完成度の高いスコアを作り上げた点に、アダンの才能と情熱がうかがえます。
第1幕では、村人たちによる華やかな群舞とテクニカルなペザントのパ・ド・ドゥにも注目です。動画は、パリ・オペラ座バレエ団より。
脇を固める名ダンサー
また、主役二人以外のダンサーの力量も試されます。女王ミルタ役はテクニック・表現ともに一流でなければ務まらず、プリンシパルやエトワールがプライドをかけて踊っています。英国ロイヤル・バレエでは現プリンシパルのマリアネラ・ヌニェスが近年ミルタ役に挑戦し、そのリハーサル映像が話題となりました。ヌニェスは元芸術監督モニカ・メイソンの指導の下、役を深めていきます。
3:05~:視線についてアドバイスです。ミルタは最初ベールをつけたまま舞台を移動します。その後ミルタがベールをとって、初めて顔が見える登場シーン。顔を斜め上に向いたときに目線を少し落とすこと、そしてピタっと目線を定めることで威厳を出すように注意しています。そして腕を大きく使うのではなく、厳格にポジションを守ること。こうすることでミルタの持つ力と冷たさが演出されます。
6:10~:腕を柔らかく使いすぎないように注意しています。厳格さ、パワーが出る効果を指摘しています。
12:50~:ソデバスクで円を描いて回るときに左の背中を使うように、そして手が高くなりすぎないよう注意しています。
日本における『ジゼル』
日本でも『ジゼル』は古くから愛されてきました。戦後間もない1950年代には、松山バレエ団の森下洋子さんがこの作品を通じて日本人バレエダンサーとして国際的評価を得ています。森下洋子さんは「東洋の真珠」と謳われ、英国や米国でも『ジゼル』主演公演を行い絶賛されました。この役を200回以上も踊ったともいわれ、その安定したテクニックと細やかな演技で世界の観客を魅了しました。
日本初演は戦前に遡りますが、本格的な上演は戦後のバレエ復興期に行われました。東京バレエ団では1966年に初演を行い、以後定番レパートリーとなっています。
近年では新国立劇場バレエ団やKバレエカンパニーなどが定期的に上演し、日本人キャストでも水準の高い舞台が作られています。2021年には東京バレエ団が初演180周年を記念してラヴロフスキー版『ジゼル』を上演し、芸術監督の斎藤友佳理さんが「古典で最も演劇性の強い作品」として次世代に演技を伝える指導を行ったことがニュースになりました。斎藤さん自身が、ジゼルを当たり役にしていました。「ジゼルは第1幕の村娘と第2幕の亡霊という二役を一人で演じ分けねばならず極めて難しい。生と死、現世と異界というテーマを描く典型的なクラシックバレエでもある」と語り、演技と技術の両面でダンサーに高い資質を求める作品だと強調しています。
日本の観客にも『ジゼル』は特別な人気があります。悲恋の物語や幻想的な世界観、日本人好みの叙情性が受け入れられ、上演のたびに高い集客を誇ります。2025年、新国立劇場バレエ団が芸術監督・吉田都さんのもとで英国ロイヤル・オペラハウスに『ジゼル』を引っ提げて遠征公演を行いました。吉田都さん自身も英国ロイヤル・バレエ団在籍時代にジゼルを代表役の一つとしていました。彼女が演出に携わった新国立劇場版『ジゼル』はロンドンの観客からスタンディングオベーションで迎えられ、日本のバレエ水準の高さを示す出来事となりました。
※ 小野絢子(あやこ)さんと奥村康祐さん。
このように『ジゼル』は日本においても古典バレエの中核をなす演目で、多くの舞台芸術ファンを惹きつけてやみません。公演後にはカーテンコールが何度も続き拍手が鳴り止まないことも珍しくなく、作品が持つ普遍的な感動が世代や国境を越えて愛されています。
映像
すでに何本も動画を紹介していますが、もう数本紹介します。
※ アレッサンドラ・フェリとミハイル・バリシニコフによる、伝説的なペアです。
※ マリインスキー・バレエ団のディアナ・ヴィシニョーワが『ジゼル』を語ります。
※ ディアナ・ヴィシニョーワとセルゲイ・ポルーニンによるフルバージョンがこちらです。
※ エフゲーニャ オブラスツォーワのハイライト集です。
今回は、『ジゼル』についてでした。ご覧いただき、ありがとうございました。
バレエ作品に関してはこちらにまとめています。ぜひご覧ください。


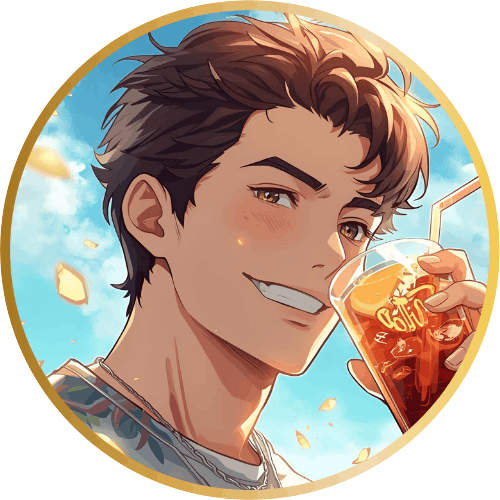



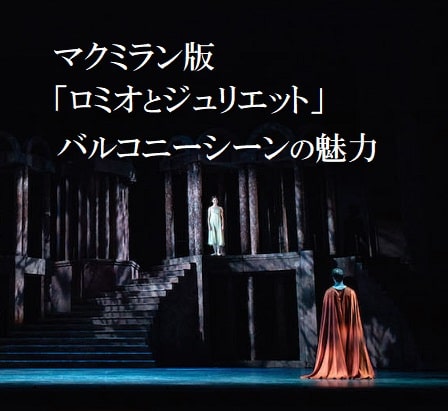
.png)
